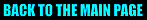ステアリング奥のメーターナセル下に,二つのつまみがある。


左側に見えるのは,チョークノブ。右側に見えるのは,純正クーラー装着車にはついているアイドルアップのための調節ノブだ。右のつまみをなんぼ引いてもまずかからない。それどころかへたに引いていたら,始動時に回転が上がりすぎて,エンジンの摩耗を早めてしまう。
左のチョークノブをつまんで思い切り引く。今日は冬の寒い日。100%手前まで引っ張ろう。思い切り引いた状態で,イグニションをひねる。この場合は,アクセルは踏んではいけない。
何回転かのクランキングの後に,火が入る。すぐに2000回転ほどに回転が上がっていく。そのままにしておくと,さらに上がろうとするので,チョークを少し戻して1500回転程度に落ち着かせる。ずっと握っておくのは面倒なので,ノブを右にひねって,その場で固定する。この状態でしばらく暖機運転だ。
メーターのチェックもやっておこう。

まずは,左上の時計から・・・こいつは,アナログである上に非常に気まぐれ,この時計で時刻を知ろうと最初から思ってはいけない。迷わずに腕時計で現在時刻を確かめて,中央のつまみを引っ張り正しく合わせる。これで,今日一日は時計としての機能を果たしてくれるだろう。
左下は,オイルプレッシャーゲージ。暖まってくると,低い回転では少ししか針が動かない。走り出したら,ある程度上がるはずなのでよしとしておこう。オイルは常日頃から気にかけているしな・・
右上の水温計は,始動時にはしっかりチェックだ。暖機運転は,せめて一番左の線を針が越えるまでつきあってあげよう。古い車,オーバーヒートも考えられる。(もちろん,本来の性能としてではなく,冷却系の漏れなどで・・)きちんと働くかどうか,確認する意味もある。
右下の燃料計。あまり細かい量まではあてにできないが,十分参考にはできる。トリップメーターの積算と併せて残量を考えておこう。路上でのガス欠はみっともない。古い車が止まっていたら,あぁ故障か・・と誤解されてしまう。そんな無様な姿を見せてはいけない。一般の車同様,最初はけっこう踏ん張ってくれるが,後半はあれよあれよと針が左へ傾く傾向がある。真ん中あたりでもけっこう粘るが,今回は燃費いいじゃないかと楽観してはいけない。山道を長く走るときには,余裕を持った給油が正解だ。
中央右側の速度計は止まっているときには,意味無しではあるが,CHGランプが消えているか一応確認をしておこう。オルタが死んでしまうと,にっちもさっちもいかない。
中央左のタコは走りのスカイラインにとっては大切。もっとも電流タイプのハコスカのメーターは,追従性や正確さなど怪しい面もあるが,音だけで判断する耳タコメーターよりは,はるかに役に立つ。CDIを付けたりすると,アダプタをかませないと動かなくなることもあるので,注意が必要だ。
そうこうするうちに,水温計の針も動き出した。さぁ,いよいよ走り出そう。
 このくらい針が振れるまで回してやる頃には,チョークを戻しても大丈夫。外気温が低く,アイドリングが不安であれば,本来クーラー用のアイドルアップノブで少しだけ上げてやれば,信号待ちでストールする心配もない。では,2点式のシートベルトをきっちり締めて走り出そうか・・(取り締まりで止められても,堂々と振る舞おう)
このくらい針が振れるまで回してやる頃には,チョークを戻しても大丈夫。外気温が低く,アイドリングが不安であれば,本来クーラー用のアイドルアップノブで少しだけ上げてやれば,信号待ちでストールする心配もない。では,2点式のシートベルトをきっちり締めて走り出そうか・・(取り締まりで止められても,堂々と振る舞おう)走り出そう