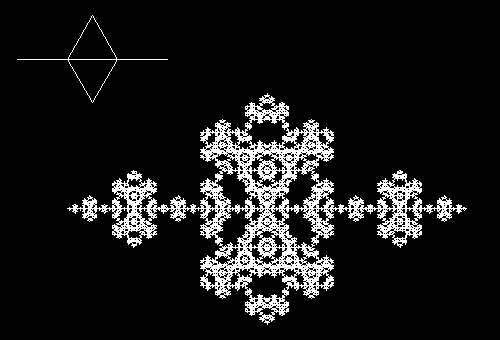 →
→
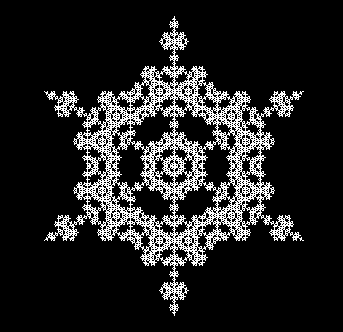
3D−LOGO
解の公式を導き出す → 判別式を抽出 → x軸との交点の個数を調べる
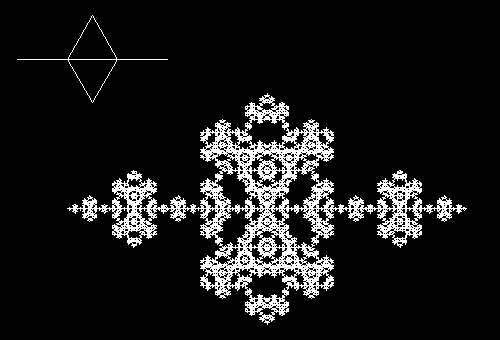 →
→
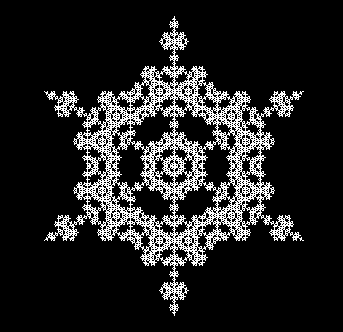
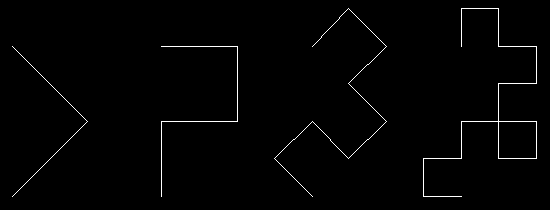 →
→
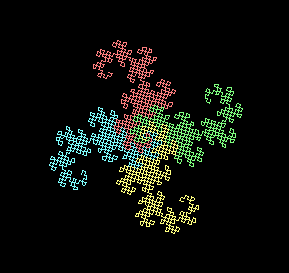
6.追記
昨年度、本校では機器の更新があり、サーバ1台(PC-9821RS)と教師機1台(PC-9821RA20)&生徒機20台(PC-9821RS18)×2教室、OSはWindowsNTとWindows95の両方をインスツールし、ワープロや表計算はNTで、マルティメディア系は95でと使い分けています。確かに便利(この資料もこの環境で作成した)になり、「コンピュータを教える(ワープロや表計算)」のはやりやすくなりました。しかし、「コンピュータで教える」ことは逆に困難(デスクトップやマルチタスクがじゃま)になったような気がします。
ソフトに関してもすばらしい機能を揃えて色々なことができるようになってきましたが、逆にその「色々できる」がじゃまをしていないでしょうか。多彩な機能があるが故に操作が難しくなり、使いこなすまでに時間がかかってしまう(教師も生徒も)。現場においては、限られた時間しかないので、結局使わず(使わせず)じまいになっていないでしょうか。授業ではなく、放課後等に興味関心のある生徒に対して使用させるのであれば効果はあると思います。
できればソフトも、「これしかできない」という単機能のを幾種類も作り、メニュー画面で使用するモジュールを選択できるのがよいのではないでしょうか。単機能であるが故に操作が簡単になり、操作の学習に時間を取られなくてすむようになる。そうすることによって、ある単元の数時間の授業時間のうち1時間をそのソフトを利用して予習や復習や知識の定着の時間に組み込みやすくなるのではないかと思います。例えば、手前ミソで申し訳ないのですが、私が自作したソフト(関数グラフ作図支援:2次曲線、2次関数、三角関数、分数関数、指数・ 対数関数がある。養成ギプス:三角比、因数分解がある。どのソフトもキーボードをさわったことのない生徒でもすぐに使えるようになるのが特徴)みたいなのを、もっと見栄えを良くして開発していただけないものかと考えています。
| Home Page | Index Page | Pre Page | Next Page |