日野山ホームへ
"比羅夫考"
海と周辺国に向き合う日本人の歴史_真島節朗著より一部引用
この高台一帯を"安土の天城"と呼び、七世紀中頃に阿部比羅夫が越の守となり、
蝦夷地討伐ための居城としたと言われています。しかし阿部比羅夫に関する資料
は少なく知名度も低いのです。ここでは各方面から情報を集めて、"比羅夫考"と
して紹介したい思います。
阿部比羅夫の祖先は、福岡県の志賀島を拠点とする安曇族で神武東征の頃に、
奈良盆地近くに移住して来た一族でした。職掌は服属儀礼という宮廷の食物共献
を仕切る役目でした。
大和国が形成されてくると、その周辺のクニに稲作技術の普及と天照大神への従
属を押し進めてゆきました。更には天皇近侍的な氏族の統率者となり、軍事・渉
外面でも活躍するようになってゆきました。
阿部氏は'あえ'という食物を意味する言葉からできた'うじな'で敢・阿閉・阿
拝・安倍とも記述されています。
阿部比羅夫の出身地は大和国城上郡辟田(現:桜井市白河)と言われています。
奈良盆地から見れば三輪山の裏手にあたり、纏向や磐余に遠くなく中央豪族の一
員であった事が分かります。
大和政権は奈良盆地の征圧が完了して国の体制ができ、外に向かって拡大し始め
る頃に交通の便利な近江国の湖北(伊香郡西阿閉)を地方支配の拠点としました。
ここは琵琶湖と古代北陸道が監視できる絶好の地で後世の事ですが、義経や木曾
義仲も ここを駐屯地としています。
また、阿部(阿閉)氏の祖となる大彦命の母は、伊香郡に因む伊香色謎命で、意
波閉神社(祭神;倉稲魂命)が高月町と余呉町にあります。そして大彦命は伊賀市
の敢国神社に祀られ、四道将軍として北陸路を進んだと伝えられています。
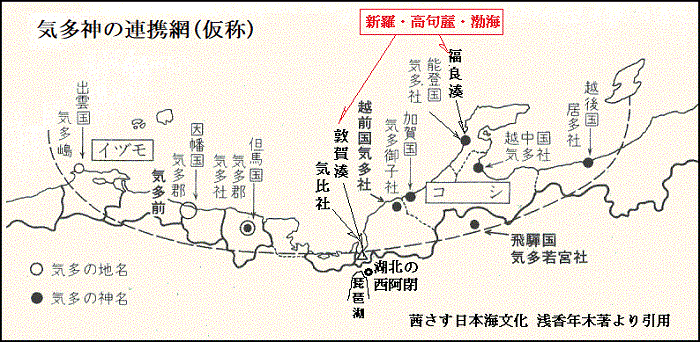
【気多の神々】
"気多"には"波打ち際"という意味があり、出雲から越後までの日本海岸一帯に官
社・郡名という政治色の強い名称で共有されていた事が分かります。これは出雲
の神と越の沼河比売の神婚伝承を裏付けるものであり、日本海へ出て北進したい
大和政権の前に立ちはだかる壁でありました。一方、連携網(仮称)内では海流に
乗って寄り来る対岸からの客人(新羅・高麗・渤海)がもたらす文物により、大き
な恩恵を受けていました。
また、能登の生玉神社伝の、土地神の多気倉長命がオホナムチ、スクナビコナ
と共に協力して怪賊退治をした話しから、気多の神々も7世紀頃には大和政権下
にあった事が伺えます。
【古代北陸道】
"科離(しなざか)る越の国"と言われるように、越の国は、それぞれの平野部が河
や丘陵で分断され、互いに孤立しているため、後世の、北陸を縦貫する陸の官道
も日本海沿岸の各港をつなぎ合わせた形をとっていました。つまり、主要な交通
手段を海運に頼る古代の北陸に特有の交通事情でありました。
 【軍神の気比神宮・劔神社】
大和政権において、気比神宮は北
【軍神の気比神宮・劔神社】
大和政権において、気比神宮は北
陸路の総鎮守社的な役割を果して
いました。高句麗使との交渉など
も行い、大陸と北方経営の窓口的
役割を持っていました。
後世になるが渤海使送迎のため
に設けられた松原客館を気比神宮
の宮司が検校するとの記事(延喜
式)からも分かります。
このように気比神の信仰が日本海
運と密接に結びついて展開してい
た事が窺われます
このような気比神宮と劔神社の神
域で敦賀湾を望む安土の天城に阿
部比羅夫は拠点を造りました。こ
の場所は、後に越前国府となる武
生に繋がる西街道の監視もできる
絶好の地で、従者郷と名付けられ、
敦賀湾と西街道を守護する意味が
あったのではないでしょうか。又
従者郷は室町期の初期の馬借集団
の稼働範囲と重なり合います。
※地図は「敦賀の神々と国家_堀大介著より引用」
"安土の天城"_平高見へ
日野山ホームへ
【阿部比羅夫の北征】
初期の大和政権は中国を手本にして、早く国の体裁を整え、朝鮮各国に負けない国
造りを見せるために、日本国の領域を名目的であっても早く遠隔地に広げたいと考え、
陸奥の地(北征)へと向かいました。
『書記』によると阿部比羅夫の遠征は三回行われている。一回目は西暦658年で
敦賀湊を出港し、北陸各湊に基地をもつ国造軍を順次合流させ、能登の七尾、伏木辺
りで勢揃いしたと思われる。(180艘混成の大船団)
当時の能登には巨大木工文化が栄え、日本海交易を取り仕切った勢力が存在し、と
り分け優れた木造船技術があり、それを操る兵士の質も能登水軍として名高いものが
あった。
大船団は能登を出発し、岩船湊(現:村上市)辺りを前進基地として北進を開始して秋
田沖(齶田浦)に到達した。 遠征一回目の目的は、混成の大水軍の演習も兼ねた征夷
(調査)遠征というのが、正しいところだろう。
翌年(西暦659年)に二回目の遠征が行われ、齶田浦(現:秋田市内)を一回目で結
んだ「友好関係の証し」として拠点(最前線基地化)とした。これにより更に北進する
際の寄港回数を省略し、より遠方まで足を延ばすことが可能になった。
この二回目の遠征の直後、日本を出発した遣唐使の一行に蝦夷が加わった。この時、
唐の天子の質問に答えて、次のように蝦夷を説明している。「都に近い方に熟蝦夷が
います。これは毎年朝貢してまいります。その先には鹿蝦夷がいて、更に遠い処に津
軽の蝦夷がいます」とし、これは唐の天子に、遠隔地まで日本国の配下にある事を示
したかったのだと思います。
三回目の遠征を『書記』では「三月に阿部臣を遣わして、船師二百艘を率て、粛慎
国を伐たしむ」これが六年三月、比羅夫三回目の遠征の書き出しである。討伐する相
手が蝦夷ではなく粛慎に変わった。 西暦660年 陸奥の蝦夷を水先案内人として渡
島まで進み、粛慎(みしはせ)を討ちました。渡島(わたりのしま)は、現在の北海道
と言われています。
【比羅夫の北征に纏わるエピソード】
◇『書記』に天智天皇即位の年の平穏な日々を記事として『近江の国、武を講う。
また、多に牧を置きて馬を放つ。また、越の国燃ゆる土(アスファルト)と燃るゆ
水(石油)献る』と蝦夷からの石油の献上を掲げている。
◇北海道開拓の明治時代に海将・阿部比羅夫を英雄として讃え、道内を走った蒸気
機関車に「比羅夫号」と名付け、羊蹄山西側には「比羅夫駅」があって、現在も
豊富な温泉地やスキー場を利用する行楽客で賑わっている。
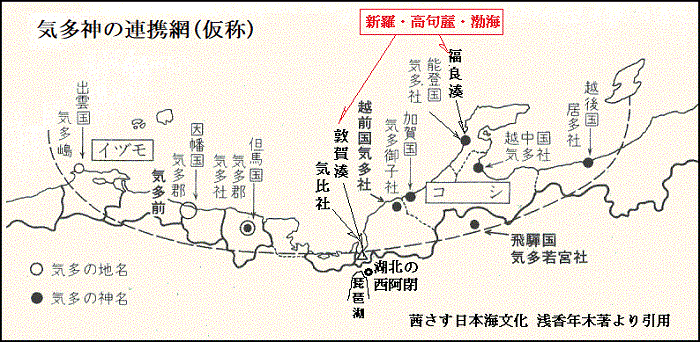
 【軍神の気比神宮・劔神社】
大和政権において、気比神宮は北
【軍神の気比神宮・劔神社】
大和政権において、気比神宮は北