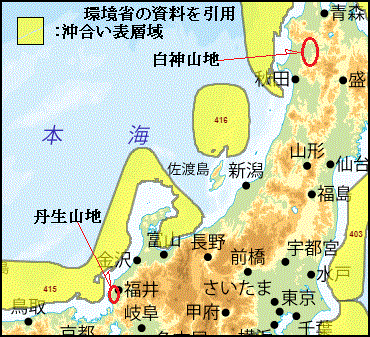糠浦にある円光寺が創設された神護恵雲二年(768)より何百年の前、出雲の国よ
り五家族19人 の人が反り子(そりこ)という舟先が高く反っている舟で対馬暖流に
のり糠浦に漂着した話が河野村の伝説として今でも語り継がれ、また反り子舟の着
いた場所は現在、反舟という地名になっていて、糠浦の守護神社は十九社神社と言
われています。
この滝に伝わる白竜は、出雲の国から乗った19人の舟の廻りを見え隠れするしな
がら舟が荒波で転覆しないよう己の身をはって守り続けて、ここ越前糠浦まで辿り
着いたそうです。
白竜は糠浦の浜へ19人を上げた後、日本海の荒波で傷ついた体を癒そうと糠海岸
の岸に沿って泳いでいた処、白い湯気の立つこの滝を見つけ、白竜はきっとこの上
に温かい水のたまった池があるだろうと思い滝を登り進んだところ、そこには雄池
と雌池が杉の木立ちの合間から見えた竜は安心して、その池に飛び込み体を休めた
と言われている。(白竜の滝)
後にその池は湯谷と呼ばれ人が住みつき杉山集落になったが、地滑りにより、現
在の杉山地籍に移住して今日に至っている。
(忘れまじ杉山の歴史_大山孝男著より)
杉山の名の由来
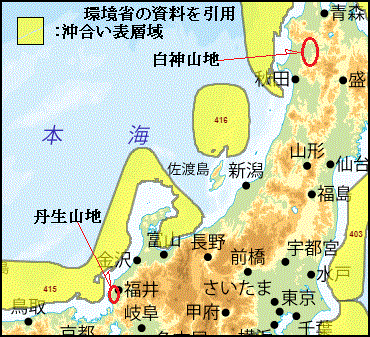
【対馬暖流と沖合い表層域】
杉山は丹生山地にあって、過っては 杉やブナの大木に囲まれた樹海の真っただ中にあ
りました。 ここには対馬暖流等の海流によって出来る沖合い表層域があり、これが魚や
植物に好環境を与えると言われています。 厨浦の厨城山の山頂付近には今でも直径70cm
〜100cmのブナ林が残されています。城崎村誌(昭和6年)には「六呂師すなわちブナの木
をもって種々の器具を製作し」とあり、ブナの大木が林立しそれを活用していた事が窺え
ます。 また、世界遺産の白神山地も同様の環境であり、日本海がもたらす恵と言って
も良いのではないでしょうか。
【太平洋戦争と供木運動】
杉山から安土に通ずる道路で、椿谷までの谷の両側には三抱えもある杉の巨木が立ち並
び、昼なお暗い場所が多かった。
この区間は雨が降りだしても、半日くらいは傘なしで通ることができた。
この巨木も太平洋戦争中、軍が使用するとの事で供出を命ぜられ、営林署からの通達で
全部で四千六百石の多くの杉の木が倒された。しかし程なく敗戦になったので供出した木
材全部が軍事用に使用されたのか知る術もない。 (忘れまじ杉山の歴史_大山孝男著より)
第二次世界大戦中、鋼船を失った日本は木船の増産を企図。個人の屋敷の巨木までを供
出する「翼賛運動」が起こされる。木と木造船をも総動員して勝とうとした。
(戦争が巨木を伐った 瀬田勝哉_著より)
【杉山の桑葉と養蚕】
好環境で育てられた葉桑は良質で杉山では養蚕が盛んであった。大勢の浜の女衆が登っ
て来て杉山は賑やかな村であった。また良質な葉桑で年3回(通常1〜2回)良質の繭を生
産した。
敦賀湾東浦(河野地区を含めた広義)一帯は農漁業の副業として養蚕が盛んであった。特
に温暖で初霜の遅い海岸部の桑葉は、晩秋蚕に重宝されて、近江の余呉村、木之本村や賤
ケ岳近くの西山村まで送られた。 夕方採られた桑葉を舟で敦賀に出し、後は陸路で明朝
早く近江に着いたようだ。明治以後、鉄道が開通すると、貨物輸送となった。
(南越前町の養蚕 増澤善和_著・忘れまじ杉山の歴史_大山孝男著より)
【果樹栽培と桃積み石】
杉山はその面積の大半が日本海に面しており、その上急斜面で平地が少なく、水の便に
も恵まれていないため田んぼがなく、桃、ビワ、梅、柿、杏などの果樹栽培して収入源と
していた。白竜の滝の近くに桃積み石という岩場があり、そこから小舟に積んで沖合で待
つ北前船まで運んだものである。
また越前水仙の出荷量は河野村で最も多く、老人二人の家でも期間中、相当多額の収入
を得ることができた。海岸べりに共同作業所を建て、そこで出荷作業を行っていたが、老
齢化が進み栽培面積も少なくなって行くことは淋しい限りである。
《追記》
江戸時代の「越前名跡考」に桃積み石(岩場)と思われる内容が書かれています。
糠浦の枝郷に杉山の名前が見え「水底岩有之岩陰大船二三艘繋間有之」とあります。
「忘れまじ杉山の歴史」によれば、白竜の滝から約百メートル糠寄りの所に、桃積み石と
いう岩場がある。ここは杉山で収穫した桃やビワ、柿、梅等を小舟に積み込んで北前船へ
運ぶための船着き場であった。今は波よけテトラポットが積み重ねられているが、この岩
場だけが昔のままの姿を保っている。
(忘れまじ杉山の歴史_大山孝男著より)